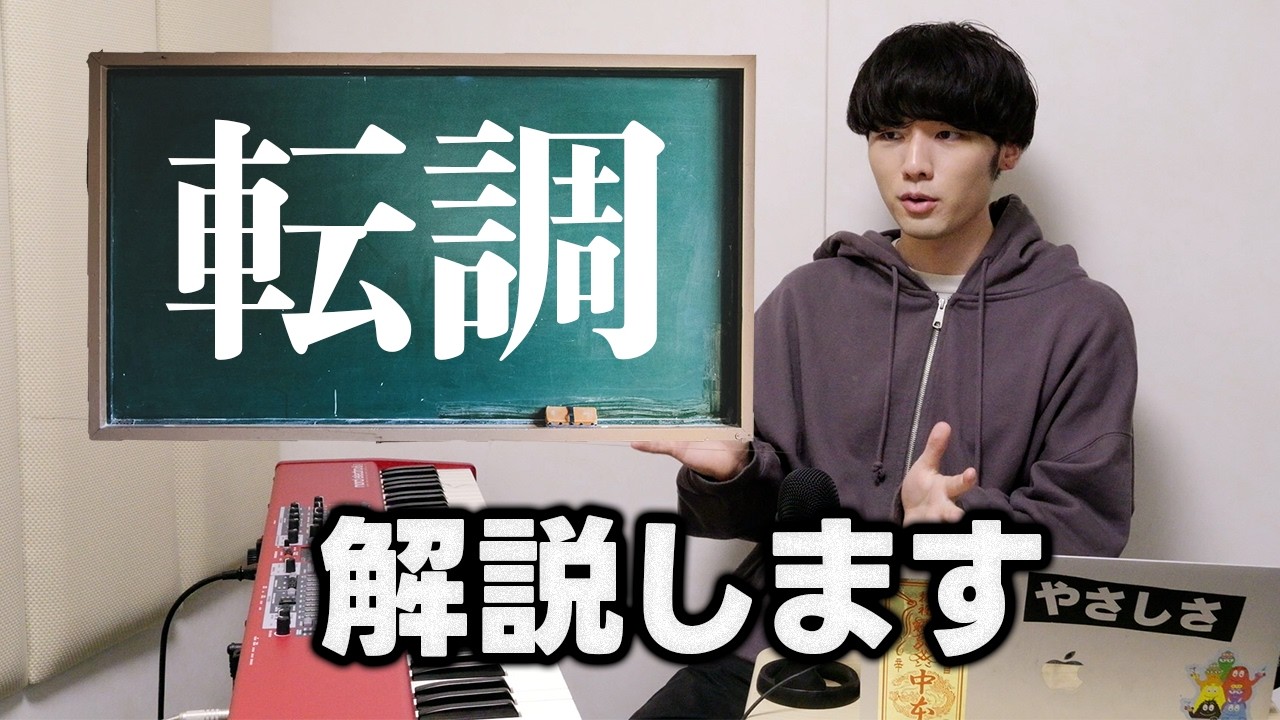はじめに:なぜ「転調」が分かると音楽が面白くなるの?
転調は、曲の空気をガラッと変える技です。盛り上げたい、景色を変えたい、意外性を出したい──そんなときに使えると、とても楽しい。まずは前提となる「調(キー)」から整理して、4つの型と実例を押さえましょう。
調(キー)=「音を選ぶためのルール」
- キーは“使用可能な音のセット”を決めるルール。
- Cメジャーなら白鍵7音。A♭メジャーなどに変われば含まれる音(♯/♭)が変化します。(A,B,D,Eが♭になる)
- メロディは“番号(度数)”の並びでできており、同じ番号の並びならキーが変わっても同じ曲に聴こえる。カラオケでキーを上げ下げしても歌える理由はここ。
- 伴奏とメロディが別キーになると強い違和感を生み出す。アンサンブルでは同じルールで音を選ぶことが必須です。
つまり転調とは、曲の途中で「音を選ぶルール(キー)を変更すること」。
これにより雰囲気を変え、ドラマを作れます。
ポップスに多い「4種類の転調」(動画での言及曲つき)
1) 上がる/下がる転調
最も分かりやすい王道。サビで半音〜全音“上げる”と高揚感が一気に増します。逆に一度“下げて”からラスサビで“上げ直す”と、跳躍が際立ち映えます。
動画での言及例
- 椎名林檎『本能』:終盤でキーを上げ、最後の山を強調。
- デコニーナ『テレパシー』:サビの前後で“下がる→上げ直し”の流れを作り、ラスサビの解放感を増幅。
- 40mP『からくりピエロ』:ラスサビ直前で一段沈み、ラストで持ち上げる設計。
使いどころ:ラスサビ、ブリッジ明け、アウトロ前。
2) 二重人格(メジャー⇄マイナー)
中心音(主音)は共通のまま、明るい/暗いのキャラクターを切り替え同主調に転調する手法。例:Cメジャーの節回しをCマイナーへスイッチ。同じ“C”を軸に統一感を保ったまま、情緒だけを反転させられます。
動画での言及ニュアンス
- 米津玄師『Plazma』:平ウタとサビでCメジャーからCマイナーへ。
使いどころ:情景を反転させたいときや、歌詞の心情が切り替わる場面。
3) ステルス転調(気づかせない)
構成音を1音だけ変える近親調へ移動。
例: Cメジャー→Gメジャー(ファ→ファ#)
Cメジャー→Fメジャー(シ→シ♭)
耳当たりが滑らかで、「いつの間にか景色が変わる」感覚を与えられます。
動画での言及例
- 嵐『迷宮ラブソング』:セクション間で近親調へスライドし、劇的すぎないのに推進力が生まれるタイプ。
使いどころ:A→B→サビのつなぎ、長尺曲の中盤リフレッシュ。
4) ぶった切り転調(意図的な断絶)
関連性の薄い遠隔調へ一気にジャンプ。
脈絡を断ち、言葉や物語のカタルシスを強調します。
強烈だが扱いは難しく、編曲/ボーカル/ミックスまで含めた“総合演出”が要。
動画での言及例
- SHISHAMO『明日も』:サビ終わり(「いいことばかりじゃないからさ」直後)で遠隔調へ飛び、感情の高まりを決定打に。
使いどころ:歌詞の転機、ブレイク後の衝撃、MVのカット替え。
まとめ:転調は“音のルール替え”でドラマを描く技法
- キーは「音を選ぶルール」。
- 転調とは、そのルールを曲中で変えること。
- 4種類の定番がある ①上がる/下がる ②二重人格 ③ステルス ④ぶった切り
転調の話って、一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、「音楽をちょっと面白くするスパイス」程度のものです。動画でもお話ししたように、椎名林檎さんの『本能』やSHISHAMOの『明日も』のように、転調ひとつで曲の景色が一気に変わります。
動画では、そうした“音の変化の楽しさ”を誰でも感じられるようにまとめました。理屈はあとからでOK。まずは気軽に読んで、耳で転調を楽しんでみてください!