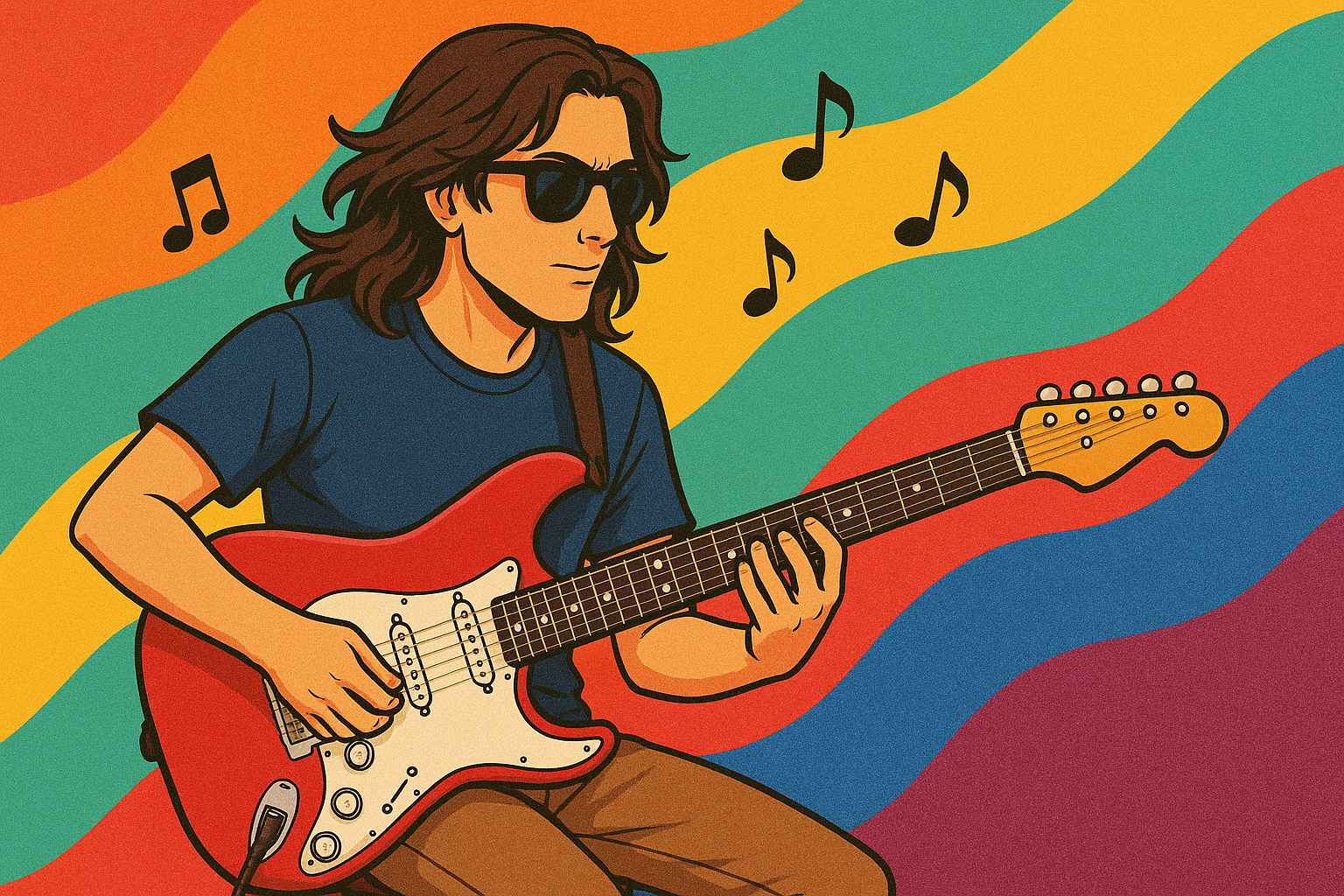そもそも“一人弾き”とは何でしょうか?
答えはシンプルです。コード(進行)×メロディ(フレーズ)×ビート(ノリ)を、途切れず一本のギターで回す練習のことを指します。
ソロギターのように厳密なアレンジを作り込む必要はありません。大切なのは “止まらず続けること”。これを行うことで、リズム感・コード感・アドリブ力を同時に鍛えることができます。
3ステップのやり方
1) コード進行を決める
オリジナルを考えるのは後回しにしましょう。時間がかかるうえ、理論不足で進行が不安定になりやすいからです。まずは定番進行を借りるのが正解です。
例:Ⅱm7–Ⅴ7–ⅠM7–Ⅵm7(Dm7–G7–Cmaj7–Am7)
Dm7をDm9にアレンジするだけでも雰囲気が大きく変わります。
2) フレーズを当てはめる
進行が決まったら、スケールはAマイナー・ペンタトニックで十分です。理屈は後回しでも問題ありません。
ポイントは「フレーズは短くすること」。長すぎるとコード進行を見失ってしまいます。1小節程度の粒で十分で、スライドやハンマリングを混ぜると自然に聴こえます。慣れてきたら同じフレーズを弦を変えてコピーしてみると音色の幅が広がります。
3) ビートに乗せる
バッキングトラックに頼りすぎないようにしましょう。自分の中でビートを刻むことが大切です。足で16分を踏み、手でストロークをしながら隙間にフレーズを差し込みます。
配置の黄金則は「3対1」。同じフレーズを3回繰り返し、4回目で少し変化させると一気に曲らしく聴こえます。この“ずらす1回”にアクセントを込めると、表情が豊かになります。
よくあるつまずきと対処法
① 進行を見失う
コードがどこまで進んだかわからなくなるのはよくあることです。
→ 対処法:フレーズを短くし、最初は極端に1音でも構いません。口でコード名を言いながら弾くと効果的です。
② 走る/もたる
テンポが安定せず伴奏とずれてしまうことがあります。
→ 対処法:足踏みで16分をカウントしましょう。難しければ8分でも大丈夫です。裏拍メトロノームも効果的です。
③ 戻りが汚い
自由に弾いたあと次のコードに戻れない場合があります。
→ 対処法:あらかじめ着地点を決めておきましょう。次のDmのルートや3rdに止めると安定感が出ます。
④ 音が寂しい
フレーズに意識が行き過ぎてコード感が薄くなることがあります。
→ 対処法:部分和音(2〜3音)で十分です。特に低音を守れば曲の骨格は崩れません。
⑤ アイデアが尽きる
同じフレーズばかりでマンネリになることがあります。
→ 対処法:入り方を変えましょう。例えば3弦から2弦に移したり、1拍前から入ったりするだけでも新鮮さが出ます。
5分クイック・ドリル
①進行を口で言う(30秒):Ⅱ–Ⅴ–Ⅰ–Ⅵを暗唱して頭に入れる。
②足で16分、手でストローク(1分):リズムの安定感を磨く。
③ペンタで1小節フレーズ(2分):短いモチーフを作り繰り返す。
④「同じ×3 → ずらし×1」(1分):アドリブを限定的に混ぜる。
⑤録音チェック(30秒):進行とリズムを確認。昨日より良くなっていたら十分です。
継続のコツは「練習を遊びに変える」ことです。テンポを変えたり、録音に簡単なドラムを重ねたりするだけでモチベーションは上がります。
上手い人の共通ループ
練習 → 記録(録音や人に聴かせる) → 分析/フィードバック → 練習法を改造。
このループを回すことで成長は加速します。最初は動画の真似で十分ですが、続けるうちに自分専用の方法が育っていきます。
まとめ
「一人弾き」は止まらず回すことが大切です。
定番進行 × 短いモチーフ × 固定ビートの三位一体で総合力が上がります。さらに「3対1」の配置で曲らしさを演出し、アドリブで課題を炙り出せます。録音と修正を毎日5分繰り返せば、確実にギターが上達します。